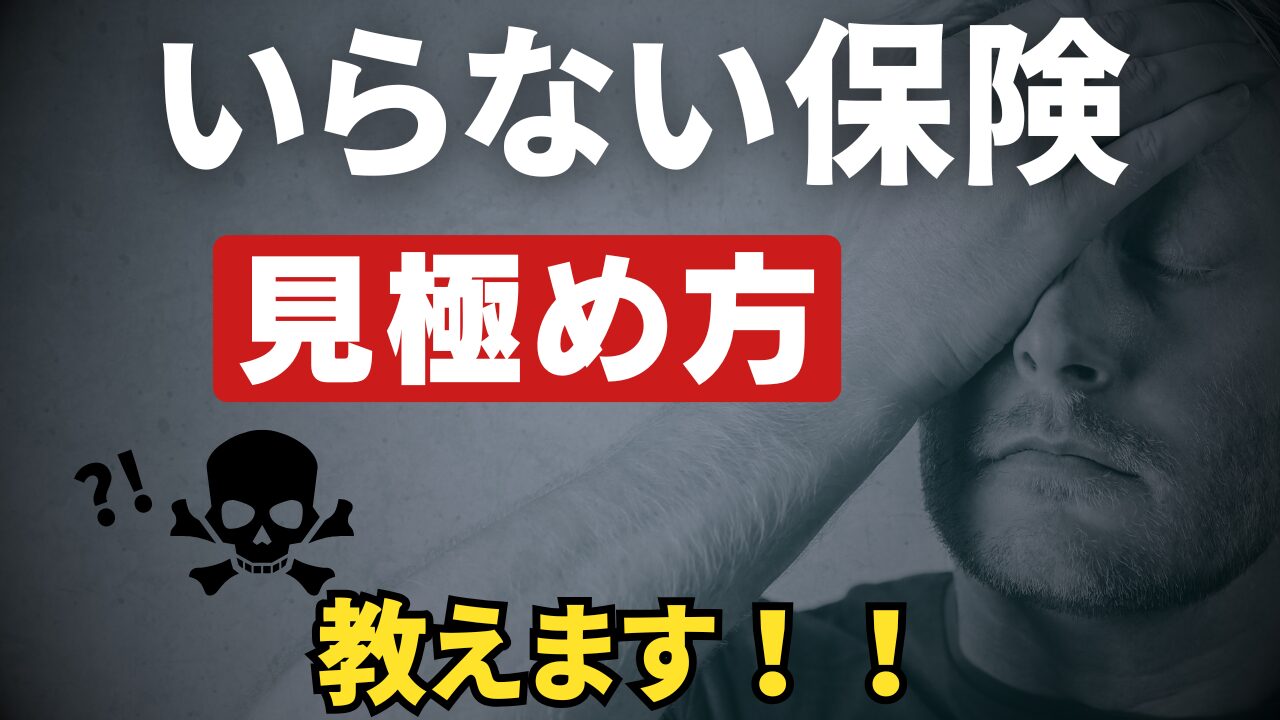「なんとなく不安だから、とりあえず保険に入っている」
「テレビでよくCMしてるし、みんな入ってるから保険は貼った方がいいでしょ!」
「親も保険にたくさん入っているし、もし何かあった時は安心やね!」
もしあなたがそのような理由で、保険に入ってしまっているのなら、毎月かなりの金額を“ムダな安心料”として払い続けているかもしれません。
僕自身も、社会人になったばかりの頃に勧められるまま生命保険や医療保険に加入し、内容もよくわからないまま毎月の引き落としを眺めているだけでした。
そんなときに出会ったのが、『いらない保険 生命保険会社が知られたくない「本当の話」』。
この本はタイトル通り、「ほとんどの保険はいらない」と、かなり攻めた切り口で保険の実態を解説してくれます。
攻めすぎて、著者は今後仕事に困らないのかなと余計な心配をしてしまうほど攻めています笑
とはいえ、感情的な保険叩きではありません。
日本の社会保障制度や数字に基づきながら、どんな保険がいらないのか どんな保険なら入るべきなのかを論理的に教えてくれる、とても実用性の高い1冊です。
この記事では、本書の要点を5つにまとめつつ、「今日からできる保険の見直しステップ」まで解説していきます。
読んだあとには、「なんとなく安心だから」ではなく、「必要だから入る・不要だから解約する」という軸で保険を考えられるようになります。
目次
① 本の簡単な紹介
『いらない保険 生命保険会社が知られたくない「本当の話」』は、保険評論家の後田亨さんと、ファイナンシャルプランナーの永田宏さんによる共著です。
2人は、長年保険の現場や相談に関わるなかで、「本当はいらない保険」に多くの人が加入している 保険会社や営業側に都合のいい情報だけが広まっているという現状に疑問を抱き、この本を書いたといいます。
本書では、日本の社会保障(公的保険)でどこまでカバーされるのか 民間保険が本当に必要なケースはどこなのか 、逆に「入らなくていい」保険はどれなのかを、一般の読者でも理解できるように、なるべく専門用語を避けて解説してくれます。
「保険ってよく分からない…」という人ほど読んでほしい、
“保険の教養本”かつ“節約本”と言ってもいい内容です。
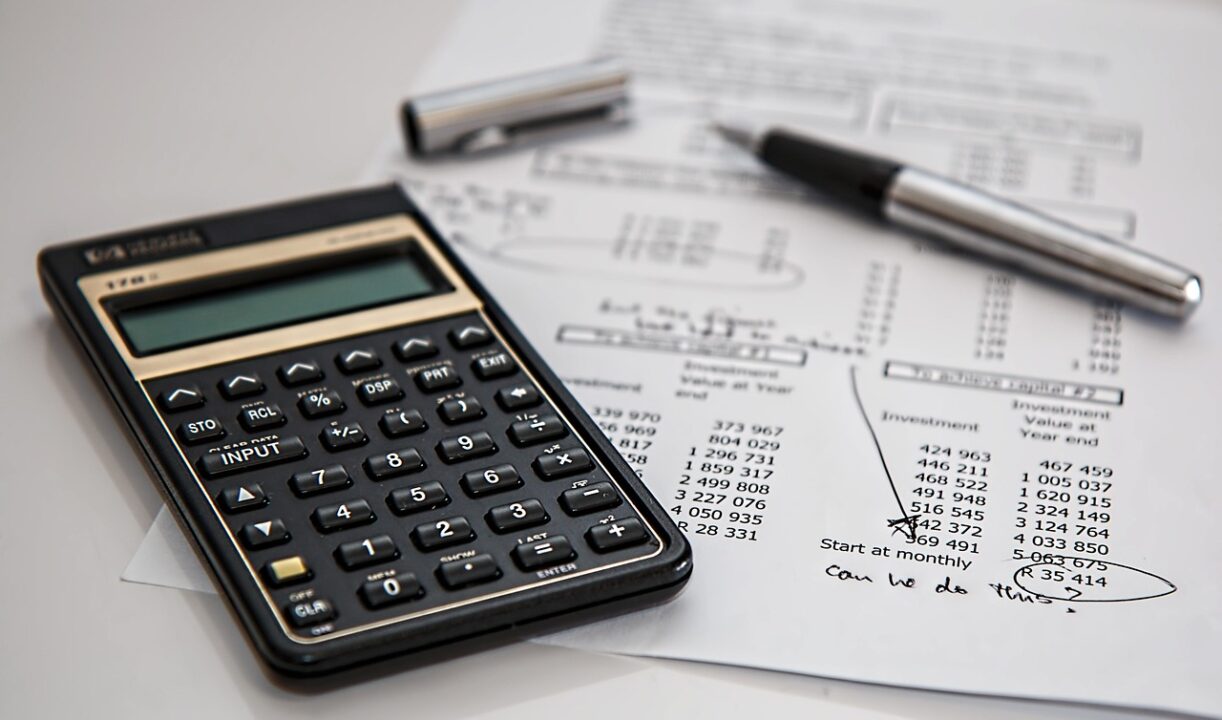
② 重要なポイント5選
Ⅰ.ほとんどの家庭で「生命保険は過剰」
日本は世界的に見ても生命保険大国と言われています。
多くの家庭が、収入に対してかなり高い保険料を払っているのが現実です。
著者はまず、「本当に大きなお金が必要になるケース」 を整理します。
収入を支えている人が亡くなったとき 大きな病気・事故で長期的に働けなくなるとき
しかし、これらの多くは、
遺族年金 障害年金 会社員なら傷病手当金
といった公的保障でカバーされる部分が大きいのです。
つまり、社会保障をきちんと理解したうえで計算すると、
「そんなに大きな生命保険はいらない」という結論になります。
Ⅱ.医療保険は“安心感”の割にリターンが小さい
次に、ほとんどの人が入っているであろう「医療保険」。
著者の立場ははっきりしています。
多くの医療保険は“割に合わないギャンブル”に近い。
日本には 高額療養費制度 があるため、よほど長期の入院や高額な治療をしない限り、医療費は一定額以上は自己負担になりません。
それにもかかわらず、「もしものために」と毎月数千円〜1万円前後を払い続けるのは、数字で見れば「かなり損をしている」ケースが多いのです。
Ⅲ.貯蓄型・学資保険は“貯金と投資の下位互換”
「貯蓄型保険」「学資保険」など、貯めながら保障も付くという商品も人気ですが、著者はこれにも厳しい姿勢です。
理由はシンプルで、途中解約すると元本割れしやすい 保険会社の手数料が高く、利回りが低い 長期で拘束される割に、リスクとリターンが見合わないからです。
「貯金や投資は自分で行い、保険は純粋にリスクに備えるものとして使うべき」というのが本書の考え方です。
Ⅳ.保険の役割は「めったに起きないけれど、起きたら人生が壊れるリスク」に備えること
本書が繰り返し伝えているのは、「保険は何でもかんでもカバーするためのものではない」ということです。
保険で守るべきなのは、火事で住まいを失う 交通事故で他人を死傷させてしまう 主な稼ぎ手が死亡・高度障害になり、家族が生活できなくなるといった、「滅多に起きないが、起きたら家計が破綻するレベルのリスク」だけ。
逆に、多くの人が入っている通院保障を細かくつけた医療保険 三大疾病保険 入院1日◯◯円タイプの保険などは、「頻度はそこそこあるけれど、あっても家計全体は大きく揺らがない」支出です。
こうしたリスクは、貯金や生活費の調整で十分対処できる、というのが本書の主張です。
Ⅴ.本当に必要な保険はシンプルに3つだけ
では、著者たちが「必要」と考える保険は何か。
本書では、ほとんどの人にとって必要なのは以下の3つだと整理しています。
火災保険(持ち家の場合は必須)
自動車保険の対人・対物(車を持つ人は必須)
掛け捨ての死亡保険(小さな子どもがいるなど扶養家族がいる人)
これだけです。
しかも死亡保険も、「公的保障+貯金で足りない部分を、必要最低限の金額で補う」というスタンスなので、多額になることは少ないはずです。
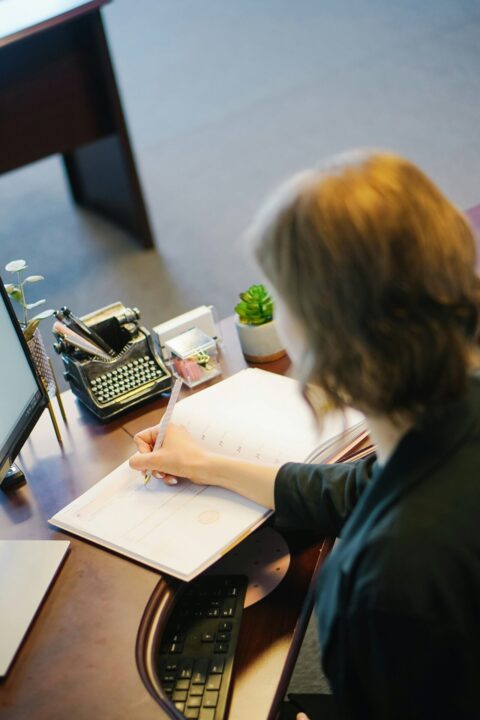
③ 今日から実践できること
本書を読んで「なるほど」と思って終わりにしてしまうと、家計は変わりません。
ここからは、実際に行動に移すためのステップを整理します。
ステップ1:入っている保険を全部書き出す
まず、現在加入している保険をすべて紙やメモアプリに書き出します。
会社名 商品名 毎月の保険料 保障内容(ざっくりでOK) 加入した目的(思い出せる範囲で)
書き出すと、「そもそも何のために入ったのか分からない保険」が意外と多いことに気づきます。
ステップ2:公的保障をざっくり把握する
次に、ネット検索や本書を参考にしながら、高額療養費制度 傷病手当金 遺族年金など、国や健康保険組合からどのくらい守られているかを把握します。
完璧に覚える必要はありません。
「思ったより手厚いんだな」と感覚的に分かるだけでも、
医療保険や過剰な生命保険への不安がぐっと減ります。
ステップ3:「本当に必要な保険」を基準に仕分けする
本書の基準に従うと、ほとんどの保険は次のどれかに分類できます。
必要(火災、自動車対人・対物、最低限の死亡保険) 見直し候補(保障額が過大、貯蓄型など) 解約候補(医療保険やがん保険など、不要なもの)
いきなり全部解約するのが不安なら、まずは「明らかに不要だと思えるもの」から見直してみましょう。
ステップ4:解約・減額の前に“保険以外の選択肢”も考える
保険を減らすのが不安な場合は、
緊急用の生活防衛資金を貯める 不要なサブスクや固定費を先に削る 万が一のときに頼れる家族・制度を確認しておくといった“保険以外の備え”も同時に作っておくと安心です。
ステップ5:「なんとなく不安だから入る」を卒業する
最後に大事なのは、今後保険の勧誘を受けたときに
「これは本当に、家計が破綻するレベルのリスクなんだろうか?」
と一度立ち止まって考えるクセをつけること。この視点さえ身につけば、もう「なんとなく不安だから」で高い保険料を払い続けることはなくなるはずです。

④ まとめ
『いらない保険』は、保険そのものを否定しているわけではありません。
むしろ、本当に保険が必要な場面 保険ではなく貯金や制度で対応すべき場面
を冷静に分けて考えることの大切さを教えてくれる本です。
この本から得られる一番大きな価値は、
「感情」ではなく「数字」と「仕組み」で保険を選べるようになること。
保険料を見直すことは、家計の固定費を改善する最も効果的な方法のひとつです。
もし今、毎月の保険料に少しでもモヤモヤを感じているなら、『いらない保険』を手に取って、あなたの保険との付き合い方を根本から見直してみてください。
きっと、“本当に守りたいものを守るためのお金の使い方”が見えてくるはずです。
保険で浮いたお金で資産形成をしたり、大切な人と大切な時間を過ごせるようにしましょう!
では!